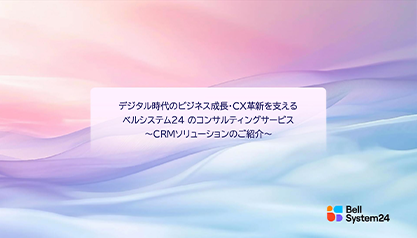雇用の流動化や働き方の多様化が進むなかで、業務における知識やノウハウを社内に蓄積することが以前よりも難しくなっています。そこで注目されているマネジメント手法が、ナレッジマネジメントです。
ナレッジマネジメントを行うことで、社員一人ひとりが持つ知識・ノウハウを社内全体に共有して業務に生かしやすくなります。
この記事では、ナレッジマネジメントの概要や注目される背景、種類、メリット、実践に必要な要素、導入の流れ、事例を解説します。
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメントとは、業務効率化や新たな価値の創出のために、従業員一人ひとりの知識やノウハウを、社内で共有できるようにするマネジメント手法です。
従業員の暗黙知を形式知に変換することで、組織全体でノウハウや知識を円滑に共有・活用できるようにします。
ナレッジマネジメントの概念は、1990年代に一橋大学大学院の野中郁次郎教授によって提唱されました。野中郁次郎教授が唱えた“知識創造に基づく経営”がナレッジマネジメントとして海外で注目されたことで、日本にも概念が広がりました。
なお、ナレッジマネジメントは英語で「Knowledge Management(KM)」と表記され、日本語に直訳すると「知識の管理」となりますが、単純に従業員が持つ知識を集約・整理するという意味ではありません。本質的な意味は「知識の創造に基づく経営」であることを理解しておくことが大切です。
関連動画のご紹介
ナレッジマネジメントにおける暗黙知と形式知
ナレッジマネジメントを実施するには、従業員の暗黙知を形式知に変換することが欠かせません。
暗黙知とは、個人的な経験や勘に基づくノウハウのことです。一方で、形式知とは、言語や数式で論理的に説明できる知識を指します。
▼ナレッジマネジメントにおける暗黙知と形式知の例
| 知識体系の種類 | 例 |
|
暗黙知 |
|
|
形式知 |
|
暗黙知としての熟練のスキルを言語化・マニュアル化によって形式知に変換することで、組織全体での共有が円滑に行えるようになります。
ナレッジマネジメントが注目されるようになった背景
ナレッジマネジメントが注目されるようになった背景には、仕事を取り巻く社会環境の変化があります。
▼ナレッジマネジメントが注目されるようになった背景
- 雇用の流動化により長期的な人材育成が難しくなった
- 雇用形態や働き方の多様化が進んだ
- IT技術の発達によってデータ・マニュアルの共有が容易になった
雇用の流動化が進み、長期的なスパンでの人材育成が難しくなりました。加えて、テレワークの普及によって現場でのノウハウの共有が円滑に行いにくいケースも見られています。
これらの要因により、暗黙知の継承を前提とした従来の組織体制を維持することは困難になっています。
一方で、発達したIT技術はデータ・マニュアルなどの形式知の共有を容易にしました。そのため、ナレッジマネジメントについては以前よりも実施しやすい環境になったといえます。
このような環境において効率的に知識・ノウハウを蓄積する方法として、ナレッジマネジメントが注目されています。
ナレッジマネジメントの種類
ナレッジマネジメントには、ベストプラクティス共有型や専門知ネット型、知的資本型、顧客知共有型などさまざまな種類があります。
-
ベストプラクティス共有型
ベストプラクティス共有型は、日々の業務における成功事例や優秀な従業員のやり方をマニュアル化して共有することで、組織全体のスキルアップを図る手法です。
ベストプラクティス共有型のナレッジマネジメントを実践するには、優秀な従業員からノウハウを積極的に共有してもらう必要があります。
この際、従業員が忙しくてマニュアル化する時間を確保できなかったり、個人の成績を気にしてノウハウの共有を渋ったりする可能性も考えられます。評価制度をはじめとする組織の体制を併せて整備しておくことが重要です。 -
専門知ネット型
専門知ネット型とは、専門的な知識を持つ従業員や社外の専門家をネットワークでつなぐことで、課題の解決を円滑に行えるようにする手法です。一般的には、専門知識の集約とデータベース化を行って、FAQとして運用するケースがよく見られます。
専門知ネット型のナレッジマネジメントを成功させるには、さまざまな専門知識を自主的にアウトプットしてもらうための環境づくりが欠かせません。 -
知的資本型
知的資本型は、自社で所有している知的資本を整理して活用できるようにすることで収益の向上を図るナレッジマネジメントです。
▼知的資本の例
- 特許
- ライセンス
- 著作権
- ブランド
- 技術
- ノウハウ など
-
顧客知共有型
顧客知共有型は、顧客から得られる情報をデータベース化して組織全体で共有するナレッジマネジメントの手法です。
▼顧客から得られる情報の例- 問い合わせ内容
- クレーム対応の履歴
- アンケートの回答 など
ナレッジマネジメントのメリット
ナレッジマネジメントを経営戦略に取り入れることで、業務の標準化や生産性の向上、人材育成の効率化などの効果が期待できます。また、企業としての競争力向上にも寄与します。
-
業務の標準化
ナレッジマネジメントの導入は、業務の標準化につながります。
個人がもつ知識やノウハウを言語化・マニュアル化して組織全体で共有することで、誰でも同じように業務をこなせるようになります。これにより、特定のスキルをもつ人物に依存してしまう“属人化”の防止が可能です。
業務が属人化している場合、担当者となる従業員が休職・退職した際に、その部門の生産性が低下してしまいます。
ナレッジマネジメントによって業務を標準化して従業員全体の業務遂行能力を一定の水準に保つことで、特定の従業員の休職・退職時にもほかの従業員で補えるようになります。 -
生産性の向上
ナレッジマネジメントの導入は、業務における生産性の向上に寄与します。
業務に対する取り組み方は千差万別で、業務の達成というゴールは一つしかなくても、そこに至るルートはさまざまです。一方で、取り組み方によって効率の差はあります。
業務を効率的に行っている従業員のやり方をほかの従業員に共有することで、企業全体における生産性の向上が可能です。また、効率的な方法が再現可能になることで、従業員それぞれのスキルアップも期待できます。 -
人材育成の効率化
ナレッジマネジメントの取り組みによって、人材育成を効率化することが可能です。
既存の従業員が持つ知識・ノウハウをナレッジマネジメントによって集約してマニュアル化しておくことで、新入社員はそのマニュアルを基に業務の効率的な取り組み方を覚えられるようになります。 -
企業としての競争力向上
ナレッジマネジメントを実施することで、企業としての競争力の向上が図れます。
ナレッジマネジメントは、社員一人ひとりが組織全体を強化し、組織が社員一人ひとりを強化するという好循環を生む手法です。社員のスキルが底上げされることでチーム全体の業務遂行能力も向上し、企業全体の競争力向上へとつながります。
また、共有した知識・ノウハウを組み合わせることで、新たな知識・ノウハウを創出してイノベーションを起こせる可能性があります。これによって、さらなる競争力の強化が期待できます。
ナレッジマネジメントの実践に必要な要素
ナレッジマネジメントを社内で実践するには、知的資産が欠かせません。また、SECIモデルと呼ばれるプロセスの繰り返しや、それを行うための場も必要です。
-
知識資産
知的資産とは、社内に存在する幅広い知識・ノウハウのことです。知識資産には大きく分けて4つの種類があります。
▼知識資産の種類
種類
概要
経験的知識資産
経験に基づく知識・ノウハウ
概念的知識資産
組織が持つ理念や経営コンセプト
体系的知識資産
体系的にマニュアル化された知識・ノウハウ
恒常的知識資産
組織内で恒常的に用いられている知識・ノウハウ
ナレッジマネジメントにおいては、これらの知識資産を集約・共有しながら組み合わせて、新たな知識資産を創出していくことが求められます。 -
SECIモデル
SECIモデルとは、ナレッジマネジメントにおける暗黙知から形式知への変換と共有を行うためのプロセスモデルです。以下の4つのプロセスから成り立っています。
▼SECIモデルにおける4つのプロセス
プロセス
概要
1.共同化(Socialization)
共通の体験を通じて暗黙知を共有するプロセス
2.表出化(Externalization)
暗黙知を言語や図などによって形式知に変換するプロセス
3.連結化(Combination)
形式知を組み合わせて体系的な形式知を生み出すプロセス
4.内面化(Internalization)
形式知を実践して、経験に基づく暗黙知を得るプロセス
SECIモデルによる4つのプロセスを循環させて繰り返すことで、新たな知識資産の創出が可能となり、組織の成長と競争力の強化につながります。 -
場
ナレッジマネジメントにおいては、知識資産の共有・活用を行うための場が欠かせません。なお、SECIモデルの各プロセスごとに必要な場は異なります。
▼ナレッジマネジメントにおける場
場の種類
対応するプロセス
具体例
創発の場
共同化
- OJT
- 営業同行
- 職場での雑談
- 飲み会 など
対話の場
表出化
- ミーティング
- マニュアル作成業務 など
システムの場
連結化
- チャットツール
- 社内SNS など
実践の場
内面化
- 実務を行う現場
- 研修・シュミレーション など
ナレッジマネジメントを導入する流れ
ナレッジマネジメントを導入する際は、導入目的や管理する情報の範囲を明確にしたうえで、情報の管理・共有を業務プロセスに落とし込む必要があります。
また、ナレッジマネジメントの仕組みを構築したあとも、定期的に見直すことが重要です。
-
導入目的を明確にする
ナレッジマネジメントを導入する目的を明確にします。
ナレッジマネジメントは、経営的な課題を解決するための手法の一つです。ナレッジマネジメントの導入を検討する背景には、何らかの課題があると考えられます。
企業が事業活動を通じて社会に貢献し利益を得て活動を継続・発展していくうえで、具体的にどのような課題があるかを明確にすることがポイントです。 -
管理する情報の範囲を定める
目的を定めたあとは、具体的にどのようなスキルや知識といった暗黙知を管理して共有化するかを決定します。
暗黙知を形式知に変換する際に大切なのは、情報の取捨選択です。これまで蓄積してきた大量の情報のなかからデータ化する範囲を絞り込み、労力に見合った情報を選定する必要があります。
ナレッジマネジメントを導入する目的に応じて、スキルや知識の範囲を定めることが重要です。 -
情報を管理・共有しやすい環境を整備する
ナレッジマネジメントを運用する際は、情報を管理・共有しやすい環境の整備が欠かせません。
情報を組織全体で共有し業務を効率化するには、従業員に負担をかけずに積極的な情報共有を促せる仕組みが必要です。情報共有を業務プロセスに組み込んだり、評価制度を見直したりする方法が考えられます。
また、情報共有が行えるITツールの導入も有効です。ITツールを導入すると、SECIモデルにおける“連結化”のプロセスに必要な場としても活用できます。これにより、形式知を連結させてより実践的な知識体系を構築して管理できるようになります。
ナレッジマネジメントツールの導入メリットについてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
ナレッジマネジメントツールとは? 導入メリットや比較ポイントも解説 -
定期的な見直しを行う
ナレッジマネジメントの仕組みを構築したあとも、プロセスやデータの定期的な見直しが求められます。
見直しを行う際は、明確な目標を定めて期間を設定し、業務の効率化に対する貢献度を数値で把握する必要があります。さらに、現場の声を定期的にレビューして見直しを加えることも欠かせません。
定期的に見直して問題点を解消することで、ナレッジマネジメントが機能しやすくなってさらなる業務効率化が期待できます。
ナレッジマネジメントの導入事例
製造業において技術相談・お問い合わせへの受付業務にナレッジマネジメントを導入した事例です。
▼導入前の課題
個人のノウハウや経験に頼った属人的な対応が恒常化しており、相談者・依頼者へのフィードバック方法が担当者によってバラバラでした。また、外部の顧客に向けたナレッジの公開についても優先度に応じた調整が難しくなっていました。
さらに、承認プロセスがブラックボックス状態となっていることで、相談・依頼のハードルが上がったり、管理者による運用状況の把握が困難になったりする問題も生じていました。
▼課題の解決方法
ナレッジシステムの刷新によって、20万点を超える商品に関するナレッジを整備したうえで、従業員が持つ暗黙知をナレッジ化して応対を平準化しました。
▼導入結果
ナレッジマネジメントの導入によって、組織全体でナレッジをタイムリーに提供できる仕組みを構築できました。フィードバック方法が標準化されただけでなく、“見やすい・分かりやすい・探しやすい”ナレッジを顧客に公開できるようになり、利便性や自己解決率、満足度の向上を実現しました。
加えて、承認プロセスが明確になったことで管理者の工数削減やナレッジ管理の効率化も果たしました。
ナレッジマネジメントの導入事例は、こちらの記事をご確認ください。
ナレッジマネジメント導入の秘訣 事例紹介編
まとめ
ナレッジマネジメントによって暗黙知を形式知化し、組織内で共有することで企業全体の生産性や競争力の向上が期待できます。
IT技術の進歩とともに時代は凄まじい速さで変化しています。時代に社会的価値を提供し続ける企業であるためには、ナレッジマネジメントによって時代に合わせた組織体制を構築することが欠かせません。
ベルシステム24では、コンタクトセンターにおけるナレッジ運用について、コンサルティングからナレッジマネジメントシステムの導入、運用設計、運用体制構築まで一気通貫で支援しています。
詳しくはこちらの資料をご確認ください。
ナレッジCXデザインサービス
この記事の推奨者

Salesforce 認定アドミニストレーター
- TOPIC:
- コンサルティング